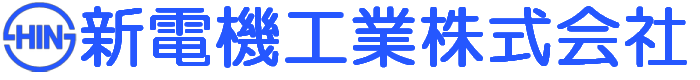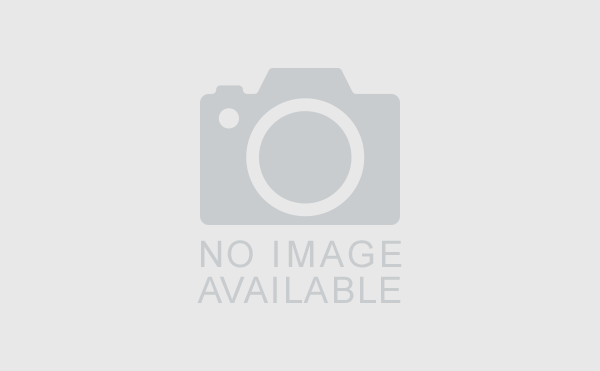濁りの哲学
20年以上前に、濁りの哲学という話を聞いたことがある。「水清ければ魚住まず」中国の古典に由来する言葉。
例えば水が清らかすぎると餌が少なくて魚が住めない状態を言い表している。
確かに、水の清らかな谷川に生息するのは、ヤマメやイワナ、エビ、などを代表とする少数の魚類ほか生物、対して、淀川の河口では海と川の合流で水が濁り餌が豊富にあるため、
海水魚、淡水魚、その他の魚類や貝類など種々雑多な生物がたくさん共生している。
つまり、水が濁っているところは餌が豊富で生物がすみやすい環境だということ。
今の人間社会に置き換えてみれば、昭和の時代は淀川の河口、令和の現代は何でも政策法律で平等という理想を追い求め、清らかな水の流れる谷川を作る発想で管理社会と言える。
政府が積極的に社会の濁りを減らしているために、人間という生物も生きづらくなり、強盗、殺人、詐欺、泥棒、うつ、様々な精神的病を患う人たちが増えているのかも知れない。
多くの人々が繁華街を好み、おじさん達が夜の酒食の店を求めるのは濁りの場所になっていて、つまり刺激的楽しい自由空間を提供してくれる場であるからだと思いませんか。
経済の効率ばかりを求め、仕事が楽しいと思えない社会にしてるのは政治家と行政、法律で理想の人間社会を作ることは出来ないという現実をもう少し理解し、もっと人間が人間らしく
楽しめる濁りの社会にする必要があるのではないかな。
「濁りの哲学」思うに自由でゆとりある精神的濁りのある人間社会に。
しかし、日本のリーダー、総理が情緒と知性豊かな人間育成に必要な国民教育に関心が無いとは、金と欲の住みにくい日本、世も末かも。
先週の金曜日の夜は、明石の大蔵海岸で社員慰労の美味しいバーベキュー会食、明石大橋がイルミネーションで綺麗に浮かび上がり、車の車列のライトが流れ、幻想の景色。
環境を変えて一時の濁りの世界で美味しい食事を楽しんでもらいました。
人口減少子供の出生率を上げるためにやってる国の政策、ほんとは子育ての苦労が楽しいと思えないから子供を作らない、まずその意識の問題をどうするか、法律では無理。
ところで、今月の末には農家さんに作ってもらっている美味しい黒豆の枝豆が刈り取りされるので、社員、従業員の皆さんに社長からプレゼントの予定、楽しみに、これも濁りの一環。
おじさん経営者の思う事・・・自分達で自分達の首を絞める行政主導の法的規制はほどほどに。・・・